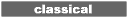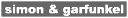モーツァルト(1756-1791) 「ピアノ協奏曲第24番」ハ短調 K.491
Wolfgang Amadeus Mozart Konzert fuer Klavier und Orchester Nr.24 C-moll K.491
モーツァルトの音楽が人の心を満たすのはその安心感にある。だいぶ前、一ヶ月だけ続けた日記サイトでそう書いた。彼の音楽の多くは、人が音楽を聞く上での常道を逸脱せず、人間の許容範囲の中で、この世のものとは思えない美しい音を奏でる。いや、人はそんな理屈を頭にして音楽を聞くわけではないから例えが悪いか?自然なメロディラインとでも表現しようか。
モーツァルトは真の意味での流行作曲家だった。聞き手が期待している音楽というものを常にイメージしながら彼らの喜ぶ音楽を書き続けた。まるで今流行のプロデューサー兼ミュージシャンみたいではないか。優れたピアニストが自ら作曲した音楽をまさに「自作自演」するエンターテインナー。その頃の彼はウィーンで絶大な人気だった。
しかし、才能ある人間は、人を喜ばせるだけの作品を書き続けることに飽きてくる。もしモーツァルトがあのまま聞き手向けの音楽を書き続ければ、晩年に(といっても30代半ばなのだが…)人気が落ちることもなかっただろう。しかし彼は次第に自分の書きたい音楽を書くようになる。つまり、エンターテイナーからアーチストになっていった。
「ピアノ協奏曲第24番」は、そんな芸術家としてのモーツァルトが試みた冒険だった。聞いてみて欲しい、その哀愁帯びたメロディを。感じてみて欲しい、この曲のもつ独特のただならぬ雰囲気を。まるで人間の悲しみそのものを代弁しているようではないか。
第一楽章の最初から弦楽器と管楽器によるユニゾン(全楽器が同じメロディを奏でること)による半音階の連続による不安げなメロディが続く。和音も七変化し、常に不安感が漂う。これが人の心模様でなくてなんだろう。おそらく当時の聴衆はこの曲に度肝をぬかれたに違いない。あまりにも当時の時代から逸脱したメロディと和音展開だったから。現代でも同じだろう。モーツァルトが好きな人もこの第一楽章のただならぬ雰囲気には最初は戸惑うのではないか。ところがフルートやオーボエ、ファゴットの音色が絡み合うことによって、不思議なことにとまどいは薄められ、華麗なアンサンブルに聞こえる。管弦楽の素晴らしい前奏部分(前奏にしては充実しすぎている!)が2分半以上続いた後に、ピアノが入ってくる。ためらいがちに始まるピアノのソロのメロディの泣かせること!常にピアノと管楽器は対話しながら音楽は進む。まるで弦楽器は伴奏のみの役割のような錯覚を覚える。
第二楽章の弦楽器による主のメロディの美しさ、そしてそれに続くピアノのこれまた優しさ。中間部のこれまた木管楽器によるアンサンブルの秀逸なこと!本当に心洗われる。
第三楽章は、再び第一楽章の雰囲気にたちもどる。しかしリズム自体が楽しげなのでさほど悲壮感ただようわけではない。でもメロディの悲しさといったら泣ける位である。途中で顔をみせる木管楽器による美しいアンサンブルが、この不安げな曲想に安堵感を与えてくれるのが救いである。
この作品をもってモーツァルトは着実に芸術家への道を歩むのだが、あまりに先進的すぎて、ウィーンの聴衆はモーツァルトの音楽を拒絶し始めた。うまくいかないものだ。
主役のピアノの素晴らしさはもちろんだが、この作品の聞き所はピアノと木管楽器とのデュエットである。これほど「音」というものを楽しめる作品はない。
−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・
私の聞いたCD
PHILIPS 422 331-2
モーツァルト「ピアノ協奏曲第24番」
「ピアノ協奏曲第25番」
内田光子(ピアノ) Mitsuko UCHIDA, Piano
イギリス室内管弦楽団 English Chamber Orchestra
指揮:ジェフリー・テイト Conducted by Jeffrey TATE
↓試聴はこちら
↓次のサイトではアシュケナージによる演奏が試聴可能
こちら
|