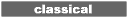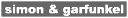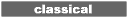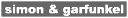「コンドルは飛んでゆく」 El condor pasa If I could
-J.Milchberg-D.A.ROBLES-P.Simon-Eng.Lyrics-
1970年、待ちに待ったサイモン&ガーファンクルのニューアルバムが発売となりました。数ヶ月前に発売され一躍トップに昇り、ずっと走り続けた「明日に架ける橋」がアルバムのタイトルナンバーとしてA面第一曲目に配置されていました。
ジャケットでは二人が縦に並びアートはじっと正面を見つめ、ポールは正面ではなく少し左側に視線が行った、全体的に暗めの水色の写真が全面にレイアウトされています。ジャケット裏はアルバム収録作品の歌詞が英語で載り、
右下に小さめに二人の写真が。こちらは、二人が歩く様子。アートは背筋を延ばし堂々としているものの、ポールは前屈みで顔が背にぶつかるほどすぐ後ろから付いてい行っているように見えます(余談ですが、このジャケットの写真で初めて二人の背丈がずいぶん違うことを知らされました)。
レコードに針を落とし、まず聞き慣れた、世界中を虜にしたあの感動的な「明日に架ける橋」。何度聞いても充実感を感じます。そしてワクワクしながら待っていた数秒間(妙に長く感じたことを覚えています、早く聞こえてこい、、と)、第二曲目に聞こえてきたのは一風不思議な曲でした。その曲はとても民族色豊かな聞き慣れぬサウンドで、いつの間にか心が暖かくもなってきました。「コンドルは飛んでいく」という変なタイトルです。
I'd rather be a sparrow than a snail
カタツムリよりも雀になりたい
Yes I would
そうさ
If I could
できるなら
I surely would
絶対に
釘になるよりハンマーになりたい
できることなら、、、、
Away, I'd rather sail away
遠くへ僕は船出したい
Like a swan that's here and gone
この地を訪れては行く白鳥のように
A man gets tied up to the ground
人は地上に縛られ続け
He gives the world its saddest sound
世界に向かい、悲しすぎる音を発している
道になるより森になりたい
できることなら、、、
僕の足の底でこの地を感じていたい
そうさ、できるなら、、
絶対にそうしていたい
いつものポールの詩とは違っています。
葉の上を這うしかないカタツムリではなく、大空を飛べる雀を、叩かれる釘ではな釘を叩くハンマー、曲がりくねる道ではなく全てを覆う森をと、暗示的であるためになお一層聞く私たちのイマジネーションを高めます。文明社会における人間ではなく、もっと広い意味での「人間」を歌うような感じがしました。
さびの部分ではこの歌の主人公はささやかな希望を歌います。遠くへ旅立つ夢。そしてその旅とは、海を超え、大陸をまたぐくらいのスケールの大きなもの。大いなる、でもはかない希望なのです。
21世紀の現在、人間は飛行機や船を使えば大陸を超えられます。でも人間は本来自らの肉体だけでは空や海を超えられません。さびの後の歌詞で主人公は、この地と共に生きる(しかない)と宣言しています。
『サイモン&ガーファンクル・伝記』(The Biography:Simon & Garfunkel by Victoria Kingston)で著者は「この童謡的な詩は「釘付けにされた自由の喜び」を、きわめてシンプルにうたっている。」と語ります。
メイン部分はすべてポールのソロ。心の高ぶりをやや押さえ気味に、まるでつぶやくように、それでいて高らかに歌う声が印象的です。そしてさびの部分はアートのソロ。軽やかで美しい高音は素晴らしいですね。
1965に南米の民族音楽グループのロス・インカスと出会ったポール・サイモンはいっぺんで彼らの音楽に魅せられました。強烈に感動したポールは、el condor pasa をとりわけ気に入りよく歌っいていたそうです。メロディが心を捕らえて離さなかったのです。やがて自ら英語の詩(この歌は南米に伝わる民族音楽の一種で、元の歌はスペイン人に対する革命を歌ったものでした)を書いた彼は、交渉の末ロス・インカスによるオリジナルトラック(器楽演奏のみ)を使用し歌を録音することになりました。オリジナル楽器によるその器楽演奏はそれだけで南米人の「心」を充分聞き手に訴える音楽だったのです。
評論家の中には、「コンドルは飛んで行く」をポールが原曲の魅力を自らの詩で薄めた作品ということで評価しない人物もいるそうです。しかし、この歌が全世界の人々の心を捕らえたことは間違いない事実。恐らくサイモン&ガーファンクルの代表作品として心に残っている曲について質問されれば、ベスト10に入るのではないでしょうか。この曲のもつ不思議な魅力は、多くの人々の耳に、今も残っているはずです。
|